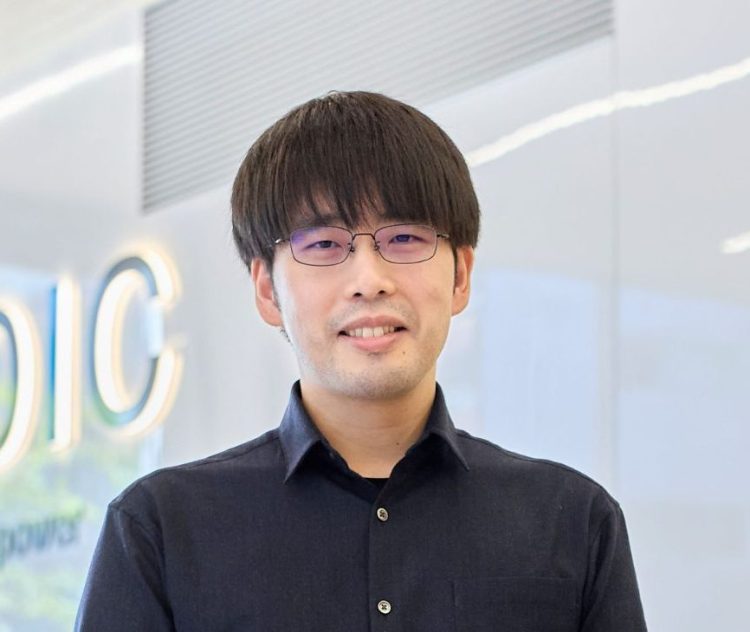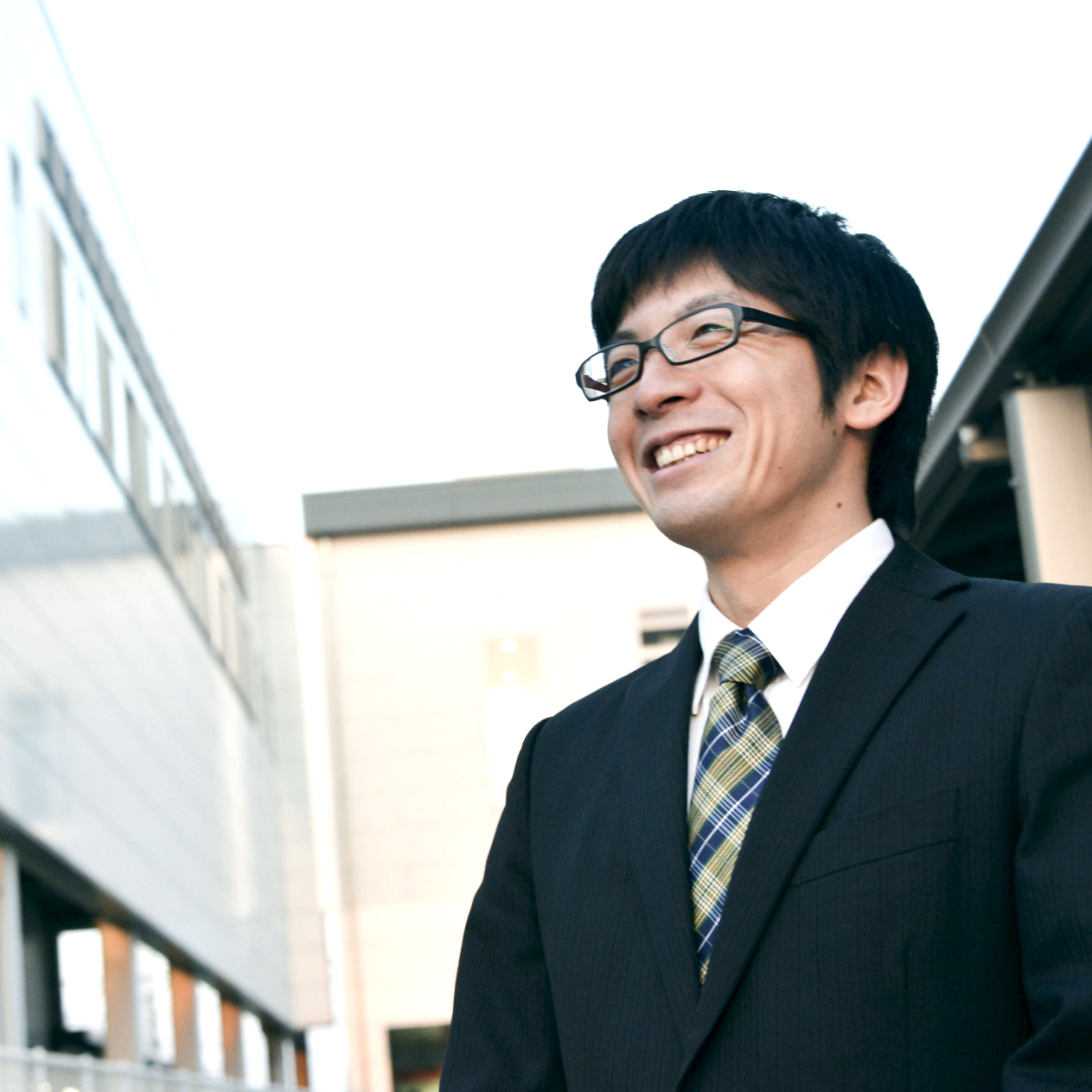お互いの入社理由と入社後の印象

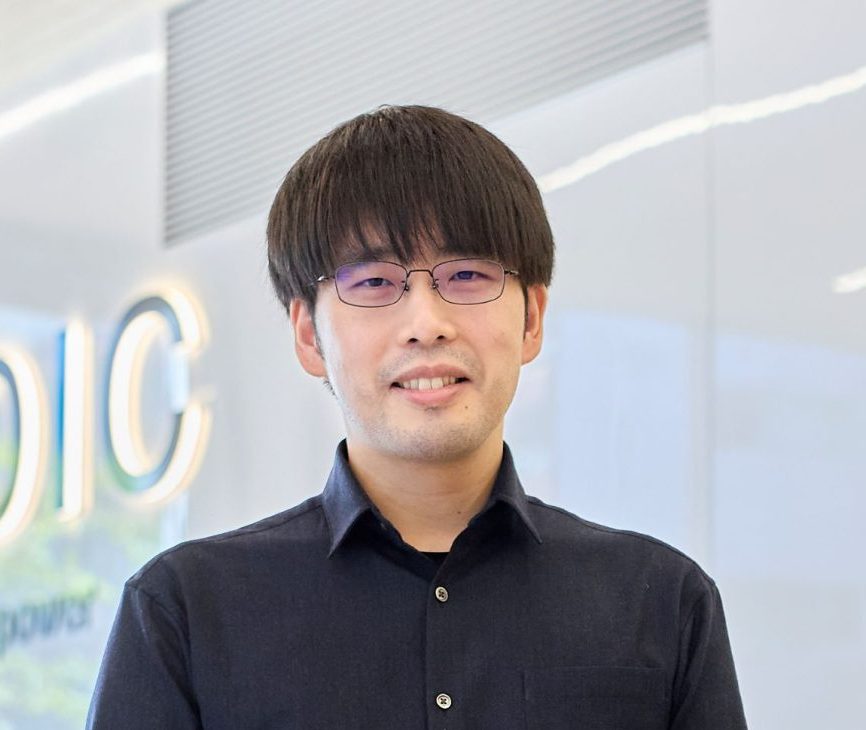
Kazuki S.
僕は県外で働くことを視野に入れて就職活動をしていたんだけど、その中で、富山県の企業説明会でタマディックに出会い、興味のあった航空宇宙の分野を手がけている会社だと知って、話を聞いて「ここなら挑戦してみたい」と思い、応募を決めたかな。
選考が進む中で印象に残ったのが、最終面談の時に、当時の本部長が学生時代に自分がこだわって取り組んでいた作品や研究について、原理やプロセスまでしっかり話を聞いていただけて、ただ表面的な質問をするのではなく、深い興味を持ってくれていると感じた事を覚えている。
技術に熱心な方が上層部にいる会社なら、自分のスキルを伸ばせると確信し、タマディックへの入社を決めた記憶があるけど、Naoya.A君の入社したきっかけは何?

Naoya A.
確か、2020年の夏、コロナ禍の真っ只中に大曽根で行われたインターンシップに参加したのが最初のご縁でした。当時、ほとんどの企業がオンライン形式でインターンを実施していた中、タマディックだけが実際に現地へ呼んでくれたんです。北海道出身の自分にとって道外へ出るのは新鮮でしたし、現地で直接社員の方々と接する機会を得られたのはとても貴重でした。
インターンでは、先輩社員が講師となって課題に取り組み、その中で社内の雰囲気の良さや空気感を肌で感じることができました。また、自分の「プレイヤーとしてものづくりに関わりたい」という想いを実現できる環境だと感じました。他の大卒や院卒の社員の方々と同じ立場で仕事に携われる点にも魅力を感じ、入社を決意しました。
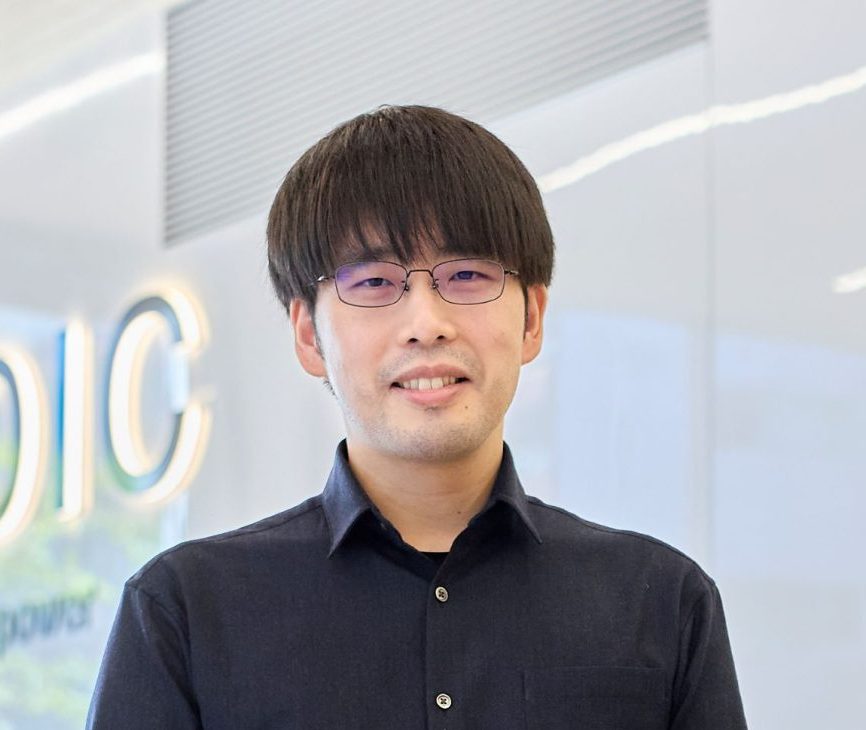
Kazuki S.
実際入社してみてどう感じる?

Naoya A.
1000人規模の大きな組織でありながら、社員一人ひとりにもしっかり目を向けてくれると思っていて、例えば、仕事のことで、結論がどうであれ、自分の意見を言えば必ず何らかの形で、耳を傾けて取り合ってもらえる環境が整っているなと感じています。もちろん、上席の判断や状況まではわかりませんが、少なくとも私の周りでは、Kazuki.Sさんや他の先輩、GMや次長の方々に話をすれば、ちゃんと聞いてくれるし、その対応に満足しています。
Kazuki.Sさんはどうですか?
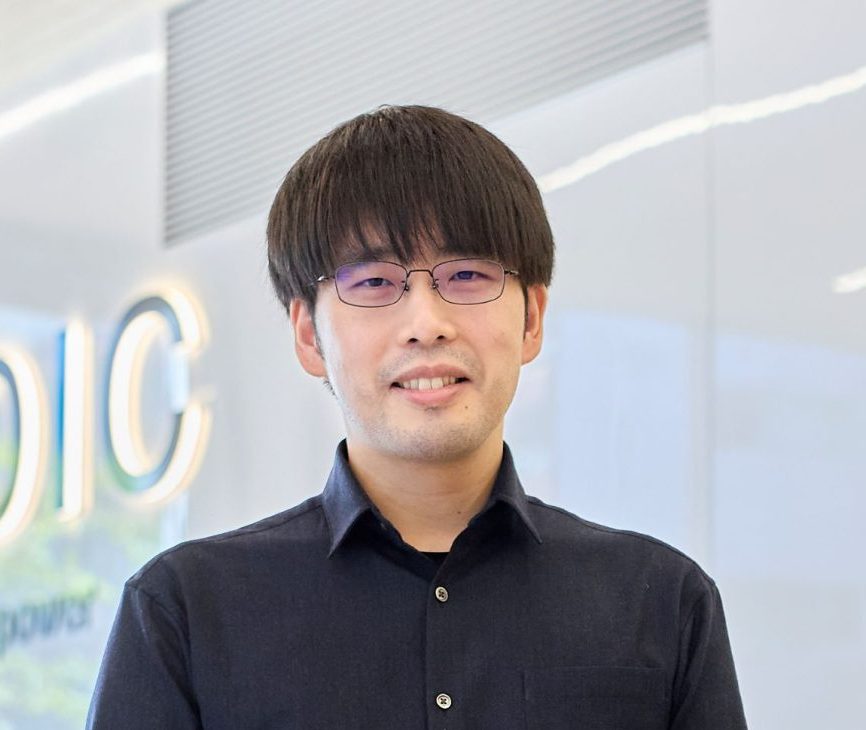
Kazuki S.
研究開発予算がしっかりと確保されているところがいいと感じていて、実際に新しいアイデアや製品を作って、それを展示できるってすごくやりがいがあると思う。作ったものが新規のお客様との関わりにもつながり、仕事につながっていくというサイクルが生まれることで社会に貢献していると感じられるところが嬉しい。
他には、会社の規模や分野的な観点で、他の場所ではできないような開発ができることも大きな魅力だと思う。特に、我々が担当しているソフトウェアや電気の分野って、世の中の注目度が高いので、上層部としても、必要性を感じていて最前線の知識や動向を持っている自分たちの意見が尊重されて提案しやすいし、展望を伝えやすい環境が整っている点が個人的にいいなと思う。その良さを理解してもらいやすい土壌があるのは安心できる部分かな。
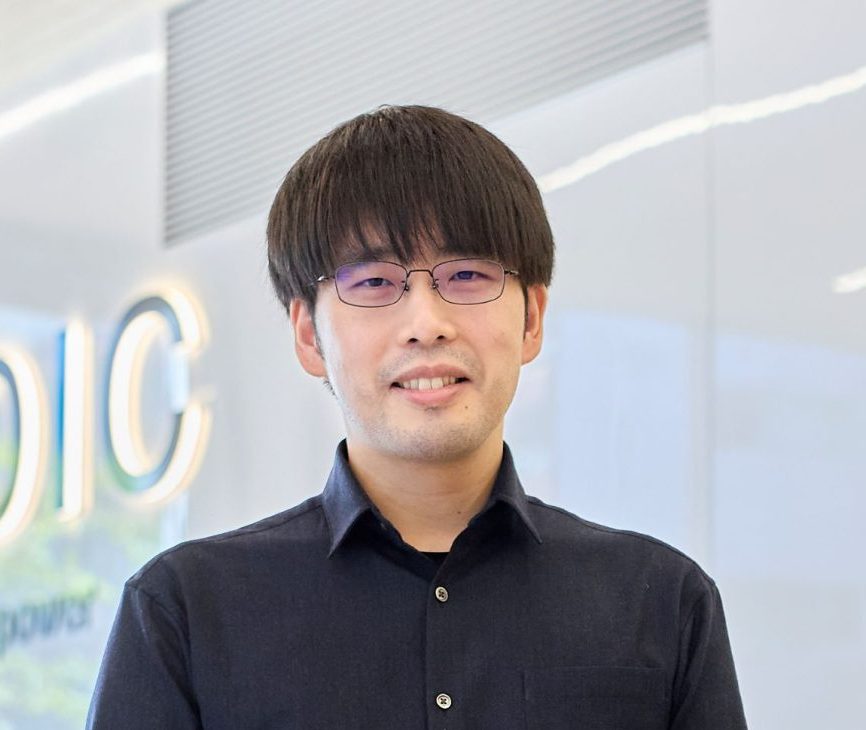
Kazuki S.
Naoya.A君は、事細かに指示を伝えなくても、最初に求めた期日の7割ぐらいの期間で、しっかり平均点以上の「的を得たあらすじが出てくる」ところは本当にすごいと思っているよ。あと文章が上手。実際、回路設計の課題を出してみたら文章を作るセンスがベテランだった。だからなんでも仕事を振りたくなっちゃうんだけど、そこはあまり偏りが生じないように、気をつけないといけないなと思っています。

Naoya A.
ありがとうございます。嬉しいです!


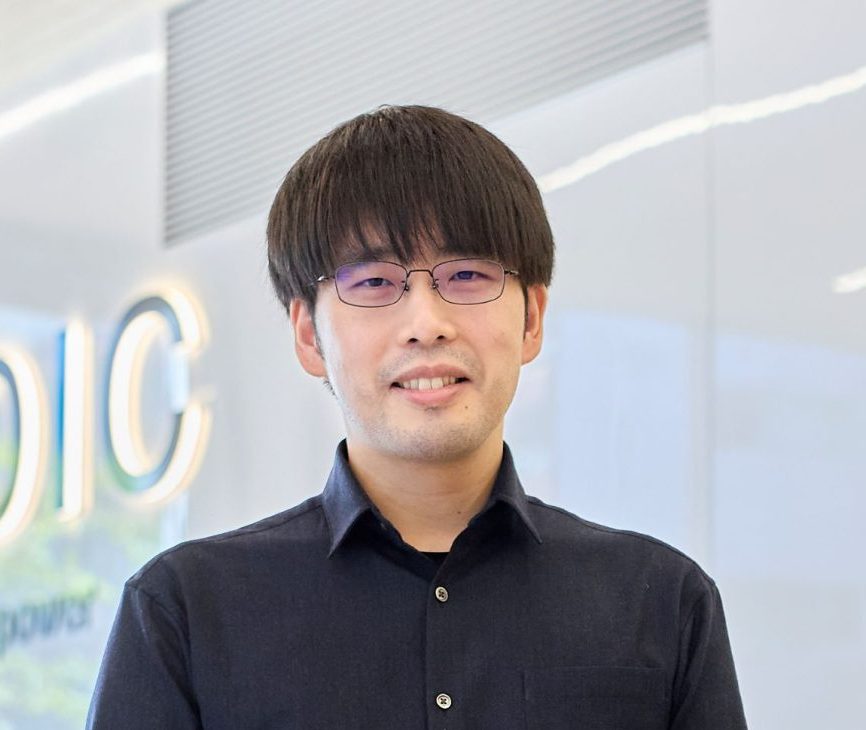
Kazuki S.
どうして良い感じの文章が書けるのかな・・・例えば、本とか読むの好き?

Naoya A.
読書家とまではいきませんが、多少は読んでいますね。実用書とかよりも、小説とか物語を読む方が好きです。
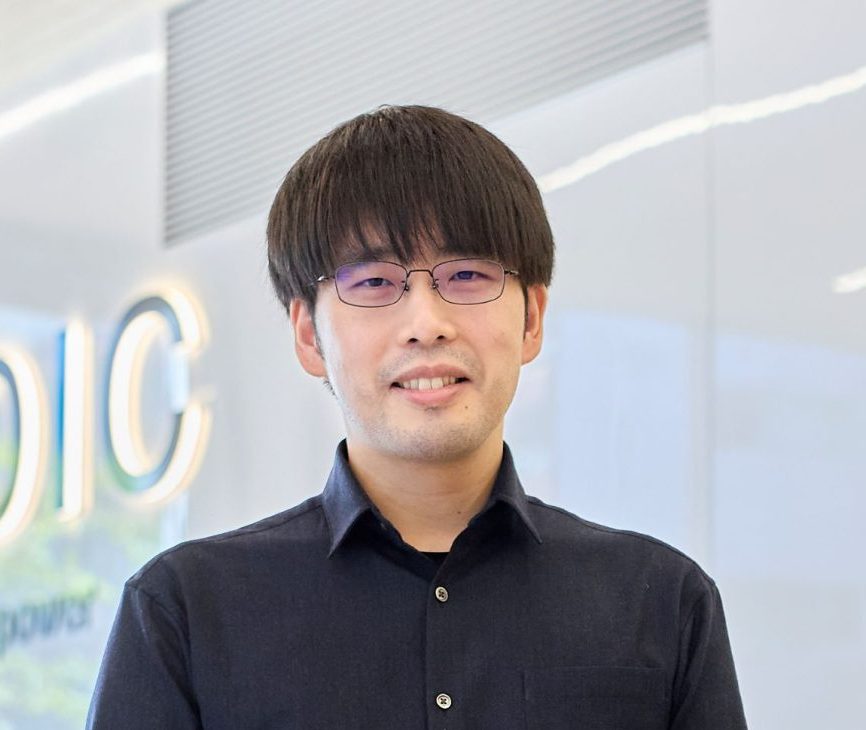
Kazuki S.
そうなんだ!そこが僕とは大きな違いだな。

Naoya A.
学生時代にレポートでかなり鍛えられましたね。高専で厳しい先生がいて、その影響は大きいと思います。どんな仕事でも、できるだけ短い期間でい最適なアウトプットを出そうと意識しています。難しい部分があっても、周りの先輩方に確認が取れる環境というか、しっかりセーフティーラインがある状態で自由に挑戦できるというところは、職場として、とても安心感があります。
先輩の凄さを実感したエピソード


Naoya A.
Kazuki.Sさんの凄いと思うところは、とにかくなんでも知っているところです。僕が学生時代何となく聞いたものや、かいつまんで知っている情報も、Kazuki.Sさんはしっかり裏付けのある知識と経験で答えを返してくださるので、本当に安心できます。それでいて、日常的にはフランクに接してくださる点も嬉しいです!
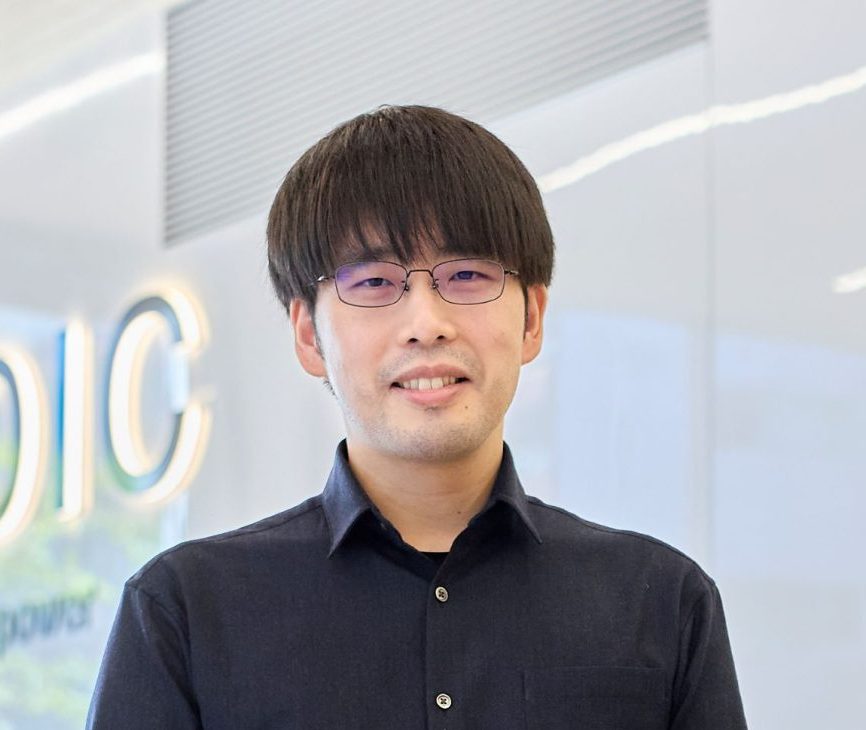
Kazuki S.
ちなみに、今も割と普段通りです(笑)

Naoya A.
結構、Kazuki.Sさんのほうからも話しかけてくださるので、じゃあ今のタイミングならいいんだと思って「すみません!」と毎日毎日、確認・質問をさせてもらっています。

Naoya A.
Kazuki.Sさんは今年の初めの頃に、大きな案件を手掛けていて。実は僕もその案件を手伝う予定だったのですが、他の仕事で忙しくて。最終的にKazuki.Sさんがほぼ一人で、複数のロボットを連携させるシステムを1ヶ月ぐらいで作られて・・・
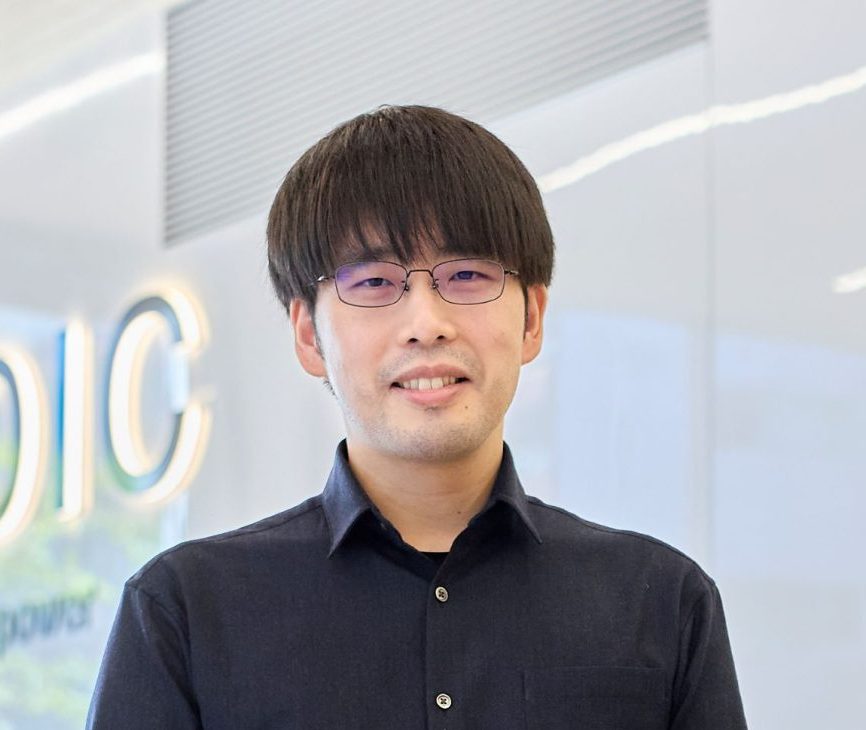
Kazuki S.
1ヶ月は言い過ぎですよ、1ヶ月半(笑)

Naoya A.
本当に構成品も多く、技術的にも色々な要素がある中、1か月半という短期間で。その後に動作確認もしっかり行わなければならなかったのですが、その全てを0(ゼロ)からこのスピード感で、ひとつのモノが形になるのかと、その時とても驚いたのを記憶しています!
エンジニアとして「わくわく」する瞬間


Naoya A.
そういえば、聞きたい事があるんですが、Kazuki.Sさんは前からロボット好きだったのですか?
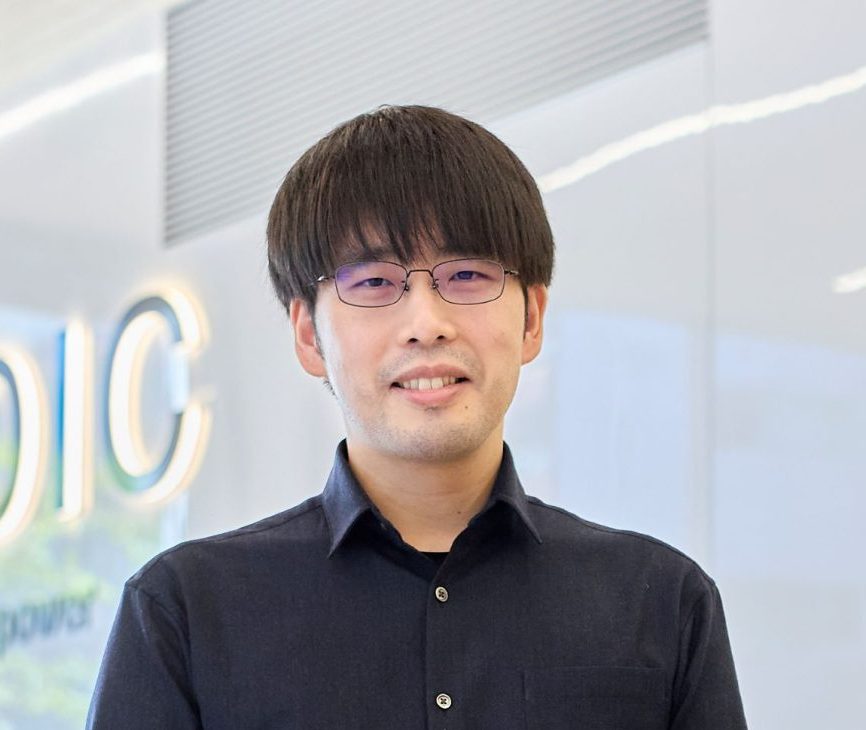
Kazuki S.
ロボットそのものというよりはFA分野に興味を持っていて、六軸ロボットだけでなく他のアプローチを探していければ面白いと思います。ちょっと工夫を加えるだけで、全然違う魅力が生まれるんじゃないかなと感じていて、この部分に未来の可能性が感じられるなと思っている。

Naoya A.
そうなんですね。僕はロボットっていう存在にずっと漠然とした憧れを持っていて、学生時代にはロボコンや高専ロボコンなんかに参加していたのですが、産業用ロボットは、ゴツゴツした機械的なラジコンみたいな感じが多く、そういうメカメカしい感じとか、思いっきり動く大きなロボットには、どこか魅力がある気がします。
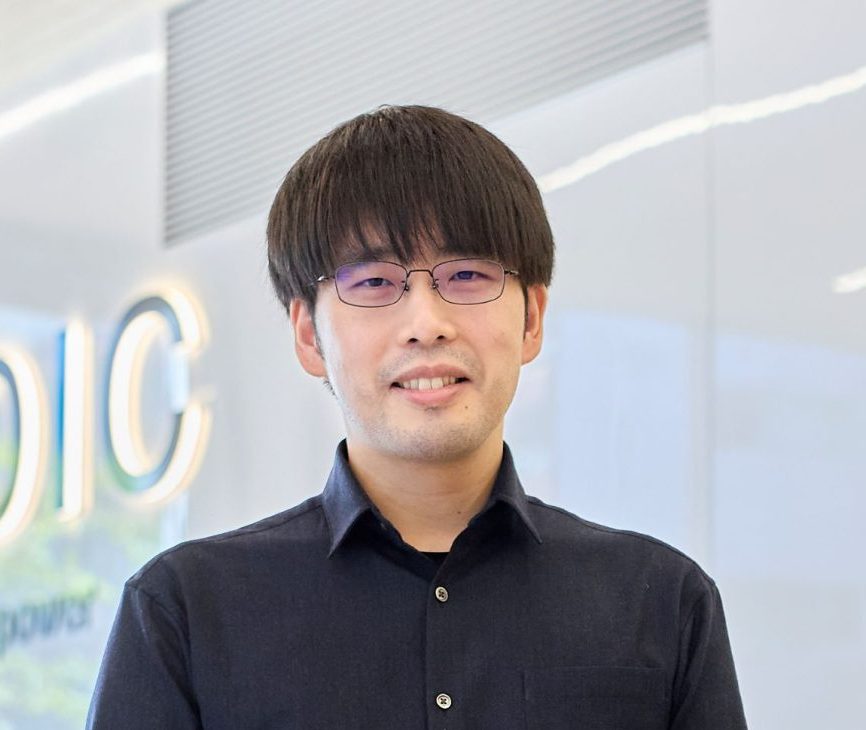
Kazuki S.
例えば、仕事で「わくわく」することってある?

Naoya A.
仕事の中だと、うまく動かなかったものがどうしたら動くのかを考えることが多いのですが、そんな時に原因がわかって、「ああ、ここか!」という瞬間があって。プログラムが動かなかった理由がわかって、一発で解決したときのスッキリ感というか、カタルシス(「浄化」を意味する心理学用語で、心の中に溜め込んだ悩みや葛藤を何らかの方法で吐き出し発散することで、問題を解決すること)がすごく気持ちよくて、それが一番ワクワクする瞬間だなと思っています。
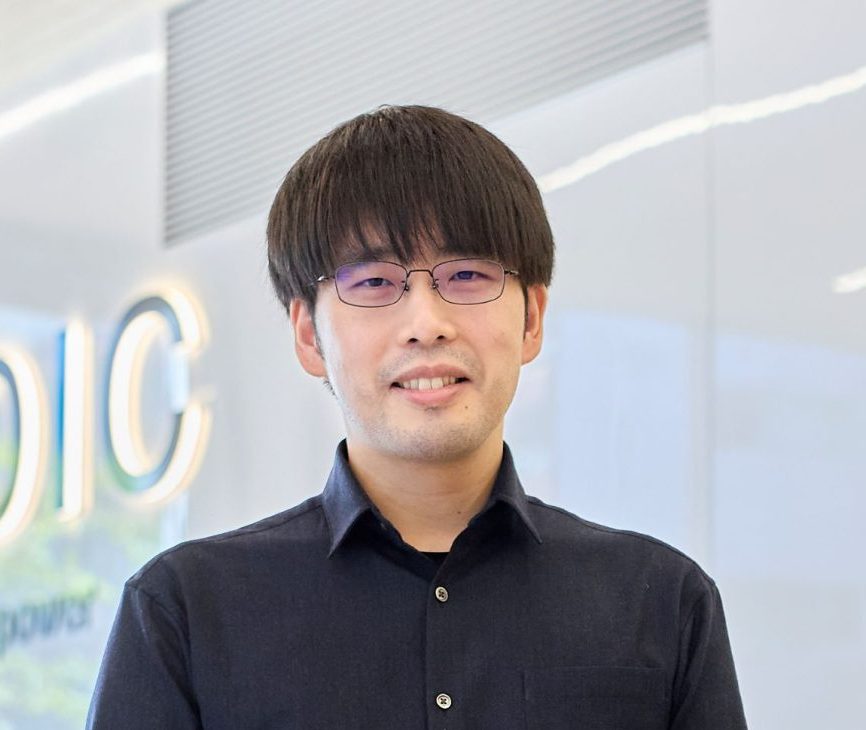
Kazuki S.
確かにね~。世の中には、ほんとに色々なものが、さまざまな人によって作られてるじゃないですか。「これは買うより自分で作った方が安く上がるし、後で何か言われても自分で対応試行錯誤がしやすいな」って気づくことがあって、そう思うと、「これやらせてもらえないかな」とか、自ら動き始めるんです。最初は難しくても、うまく進められるとワクワクするし、その壁を越えていくのが面白い。
今後の目標や将来のビジョンについて
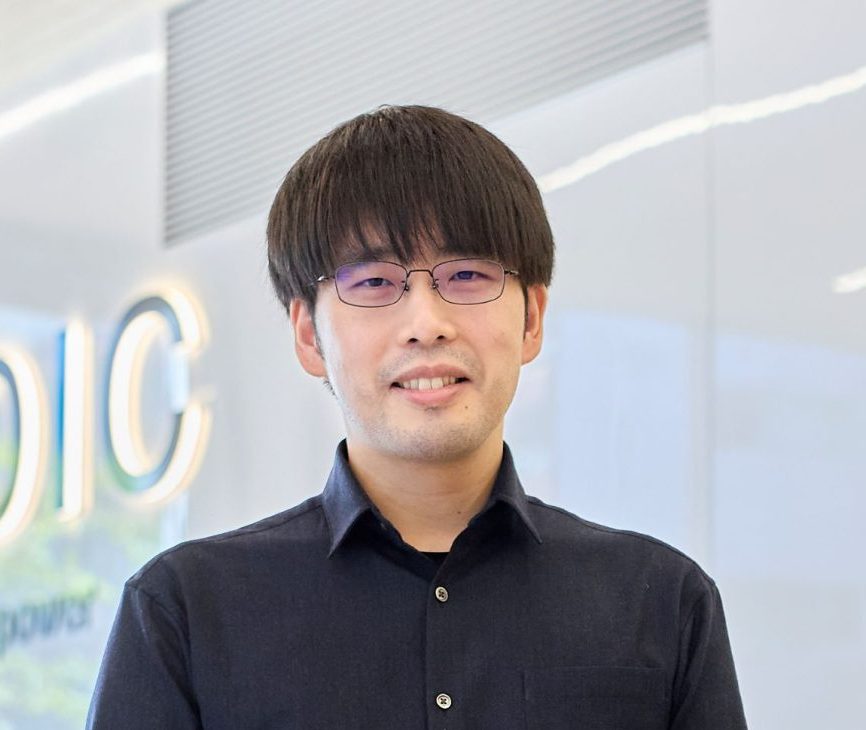
Kazuki S.
ところで、今後の目標や将来ビジョンをどう考えている?

Naoya A.
以前も話したかもしれませんが、僕は技術の使い方や研究開発を通じて、さまざまな可能性が広がっていると感じています。2年半ほどの経験の中で、やれることが増えてきたと思うので、今後はその経験を活かして、例えば異なる技術を組み合わせて新しいシステムを作ったり、課題を解決したりできるようになりたいですね。Kazuki.Sさんのように、実際にいろんな問題を解決できるような視点を身につけて、もっと成長していくことが大きな目標です。隣で見ていると、これとこれを組み合わせれば、お客さんのこの課題を解決できるっていう提案力。常にこう、何かしらの答えを持っている感じがあって、そういうところを見習いたいと思っています。
Kazuki.Sは挑戦したい仕事とかありますか?
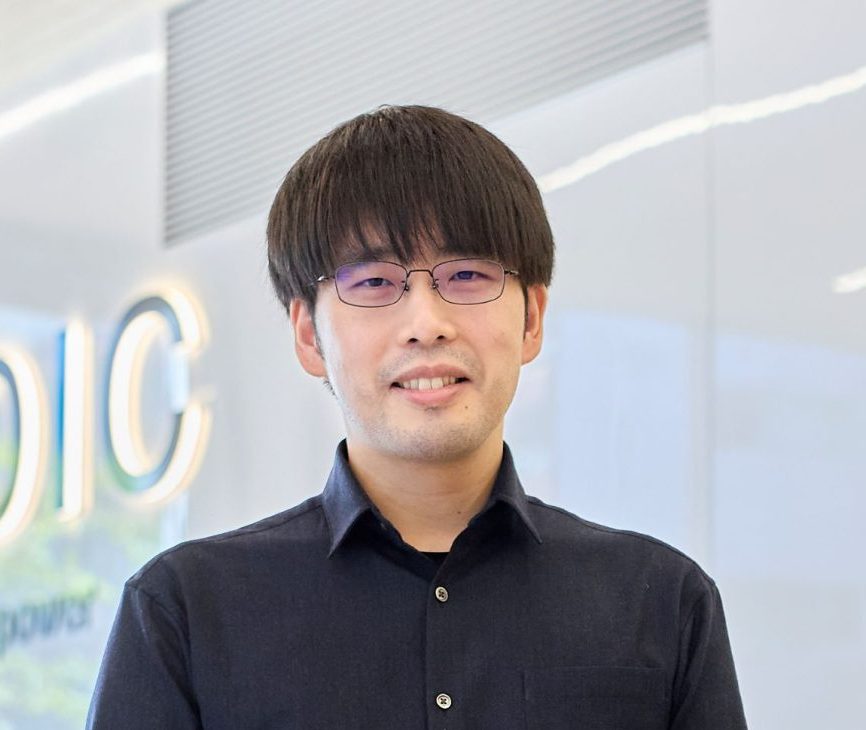
Kazuki S.
僕は生成AIを本格的に業務に導入する土台作りにチャレンジしたいと思っているよ。説明文書の作成や議事録、テストコードのひな形作成などの作業面を生成AIに移管することで、作業時間を半分に削減することが可能で、チームメンバーや上長の負荷を大幅に軽減できる。さらに、評価項目の整理や過去の仕様書に基づく新提案のセカンドオピニオンとして利用することで、見落としを防ぎ、品質向上も期待ができる。重要なのは、セキュリティの確保、生成AIの効果の周知、そして依存しすぎないようにする防止策なんですよね。それを考えて提案できることがエンジニアの醍醐味の一つでもあるよね。

Naoya A.
いつも勉強になるお話しありがとうございます!